

猫と暮らすと、ほっこり穏やかな気持ちになります(*˘︶˘*).。.:*♡
ねこがそこにいるだけで思わず笑顔になるから不思議ですね。
ネコちゃんのように自然体で生きていきたいですね=^_^=
猫の一生
誕生からあっという間の子猫時代を経て成猫となり、老猫となっていくネコちゃんの生涯を解説しています。

猫の一生は人間と比べるとはるかに短く、平均寿命は15,75歳 (ペットフード協会 平成27年度調べ)。
長生きしてもせいぜい20数年ほどと言われています。
それぞれの時期の特徴を把握して、いつまでも愛猫が元気でいられるように
共に過ごす時間を大切にし、年齢に合った接し方をするように心がけていきましょう。
猫も人も寿命というもの、こればかりはわかりませんが、人間が猫を飼う場合、
猫の寿命を考えた上で生涯飼育責任を持つ必要があります。
| 猫の年齢 | 人の年齢に換算すると(約) |
| 1歳 | 17歳 |
| 1歳半 | 20歳 |
| ※これ以降は4歳づつ歳を重ねていきます | |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 18歳 | 88歳 |
| 19歳 | 92歳 |
| 20歳 | 96歳 |
| 21歳~ | 100歳~ |
※参考:ねこ検定より
身体や心がどんどん成長する時期です。
生まれたての子猫の体重はわずか約80g~100g程度の小ささ。
その後、半年ほどで2~3kgに成長していきます。
フードも子猫用のミルクから離乳食からキャットフードに切り替わります。
この時期がとても大切で、母親猫や兄弟猫と触れ合いながら社会性を身につけていきます。
子猫期は、目にするものすべてに興味深々で活発に動き回ったり、走り回ったりする時期でもあります。
この時期にたくさん遊んであげて触れ合うことで、人間に対して警戒することなく
慣れていき、より友好的となり、猫とのゆるぎない信頼関係が生まれます。
またこの時期は、必ずワクチン接種を2回、不妊(去勢・避妊)手術をするのがベストです。
生後6ヶ月くらいになると、オス・メスともに性衝動が見られるようになり、
繁殖させる予定がない限り、きちんと避妊・去勢手術を受けさせましょう。
性衝動が抑えらえ、猫がストレスなく暮らしやすくなります。
特に懸念されるのは、メスは乳腺腫瘍などの病気にかかりやすくなるといわれています。
避妊手術はそのリスクを避けることができます。
子猫は体が未発達なため、免疫力も充分ではなく、ウイルスなどの感染によって起こる病気にかかりやすく、
重症化しやすい時期なので充分な注意が必要です。
子猫期は特に動物病院にお世話になることが多いので、信頼のおける動物病院選びも大切なポイントですね。
生後半年からわずか1年くらで体つきや顔つきが大人の猫と変わらないくらいに、乳歯が抜けて
永久歯が生え揃い、成猫の毛に生え変わります。この時にフードを成猫用のものに切り替えましょう。
要注意なのがこの時に発情も頻繁に起こってきます。
妊娠や出産を望まなければ、早めに不妊去勢手術が必要です。
1歳くらいで、猫の体の成長は一段落し、安定します。
性格は、3~4歳くらいまでは、まだまだやんちゃで、好奇心旺盛、活発な時期で遊びたい盛りです。
この遊び盛りの時期にオモチャの種類も工夫していっぱい遊んであげて、
運動させることが長生きにつながります。
子猫の時期と比べるとだんだんと落ち着きが出てくるものの、毛ヅヤや運動能力もこの頃が一番活発で
ピークといえる時期です。
あまり大きな変化がない青年期は、飼い主さんも油断しがちでこの時期の猫の病気を見逃してしまうこともあるので、日々の様子をよく見ることが大切となります。
この時期は、安定した状態で活発さは続きますが、
食いしん坊な子はついつい余分に与えてしまいがち。肥満にならないように注意が必要です。
また、成猫のこの時期にかかりやすい代表的な病気は、泌尿器の病気です。
猫は一説では、祖先が半砂漠地帯で暮らしていたので、あまり水を飲まなくても身体を維持できるしくみに
なっているのですが、そのために、体内の水分が不足しがちで、泌尿器に負担がかかりやすいといわれています。
膀胱や尿道などに結石ができる病気の総称です。結石が尿道に詰まると、排尿が困難となり、
毒素が体内を巡って命を落とす「尿毒症」ともなることもあります。
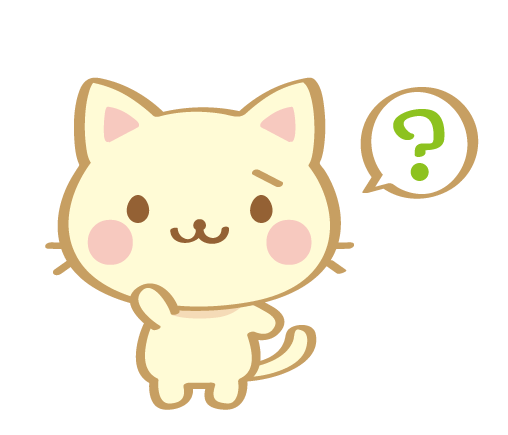

オシッコを我慢した結果、膀胱内に細菌が繁殖するなどで、膀胱が炎症を起こす病気です。
結石が膀胱にでき、炎症を起こしてしまうため、膀胱を傷つけてしまうこともあります。
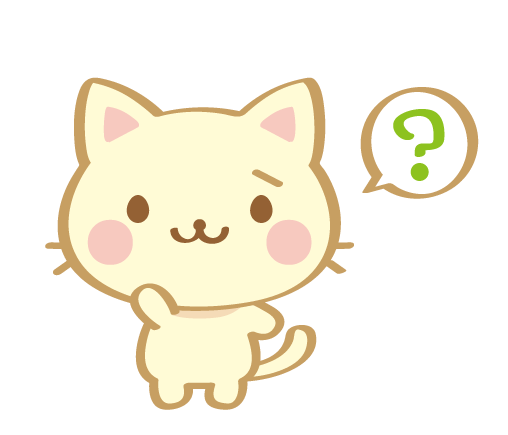
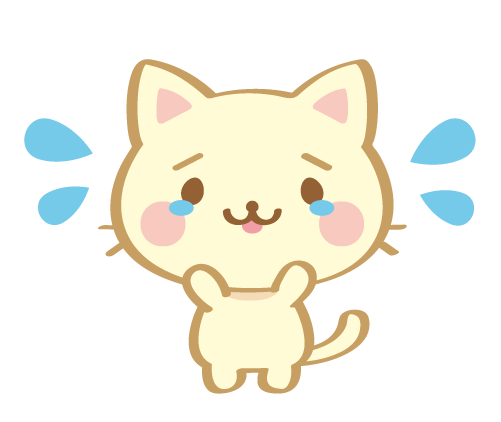
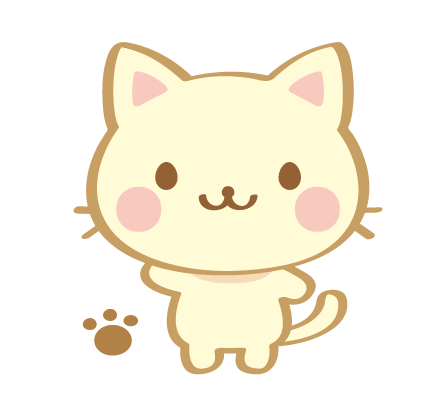
徐々に身体に衰えが表れる。
だんだんと体力も落ちてきて、行動量が減って動きもゆっくりとなり、寝ている時間が増えていきます。
なりたてシニア期ともいわれており、シニア用のフードに切り替えましょう。
顕著な行動としては、高いところに登れなくなったり、毛繕いや爪とぎの頻度が以前より減って、毛ヅヤも衰え、
口周りや全身の被毛に白髪が混じるようになります。体が硬くなったり、歯が抜けたりすることもあります。
定期的に動物病院での診察が必要になります。
シニア猫に最も多い病気といわれています。加齢に伴い、腎臓の機能が徐々に低下して、老廃物がたまる病気です。
初期症状が出にくいため、多飲多尿などの症状があらわれて、気づいたときには、
病気がかなり進行し、腎臓の機能の約7割が失われているといわれています。
腎機能をほとんど失うと死にいたります。早期発見・治療が大切です。
腎臓の機能は、完治はしないので、補液したり、吸着剤を投与して老廃物を対外へ排出して
腎臓の負担を軽くし、症状を緩和させる治療を行います。
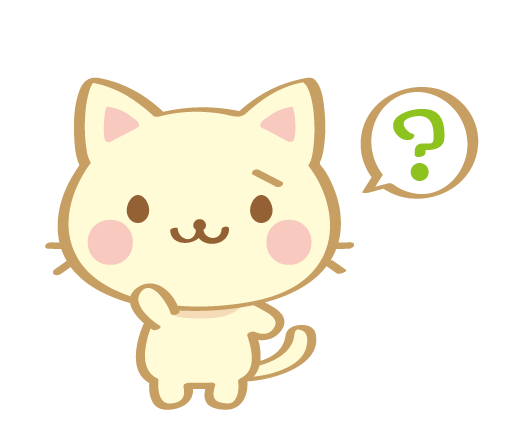


甲状腺とは、体の発育や新陳代謝を促進するホルモンをつくり出す内分泌器官のこと。
甲状腺に異常が起こり、代謝が過剰になる病気です。
ホルモンの分泌が増えすぎるのが「亢進症(こうしんしょう)」で、
この病気の主な原因は、甲状腺にできた良性の腫瘍や肥大といわれています。
症状によっては、甲状腺の切除手術をする場合もあります。
投薬や食事療法で甲状腺ホルモンの分泌量を抑え続ける必要があります。
それを続ければ、健康な時と同じような生活を送ることは可能になってきます。
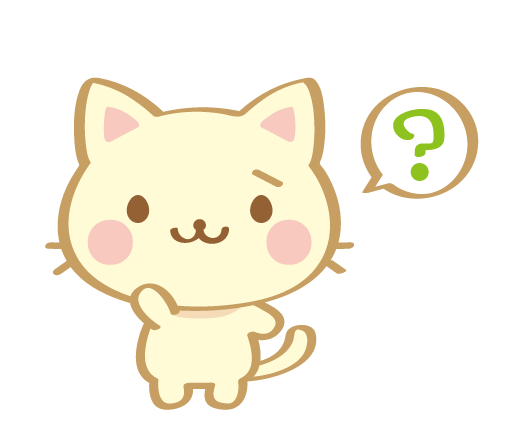


インスリンの不足などで血糖値が上昇
すい臓で分泌されるホルモン、インスリンには血液中の糖を細胞に取り込む働きがあります。
足りなくなったり、効きが悪くなったりすると血液中の糖が細胞に取り込まれず、血糖値が上昇。
肥満や遺伝の他、すい炎など別の病気に伴って発症することもあります。
完治は難しく、インスリン投与や食事療法などで血糖値を調整しながら付き合っていかなければなりません。
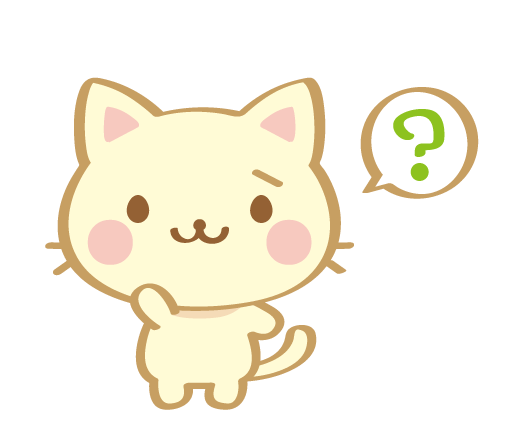


一般的には、一日中寝てばかりいるようになり、おもちゃで誘ってもなかなか遊んでくれません。
食事の量もだんだんと減り、抜け毛が増えて被毛に乱れが現われ、内臓や歯も弱くなっていきます。
この時期は、健康診断を年2回に増やし、よりいっそう身体のケアへの注意が必要となってきます。
爪が引っ込まずに出しっぱなしになっていたり、聴力や視力が衰えて反応が鈍くなったり、トイレで粗相をしたり、
ゴハンを何度も催促するなどの猫によっては、認知症の症状が出ることもあり
ます。
日頃の愛猫の様子をよく見ていち早く異変に気付けるようにしたいものですね。

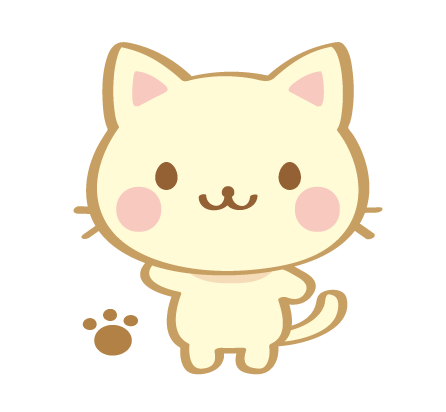
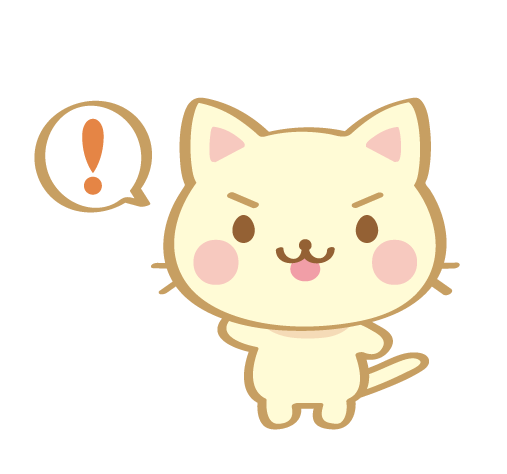
以上が「猫と人の年齢換算表」及び、
誕生から短い子猫時代を経て成猫、老猫の身体的な変化と特徴、
「猫の一生」を4つの時期にわけて猫がかかりやすい病名をあげました。
これを知っておくことで、「猫を飼う」ということはどういうことなのか、
「生涯責任飼育の大切さ」を痛感しています。
少しでも参考にしていただければ、こんなに嬉しいことはありません!
今や愛猫は愛しい家族そのもの!
大切なネコちゃんといつまでも元気で暮らせますように
心よりお祈りしています。




